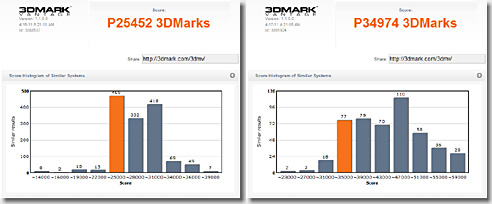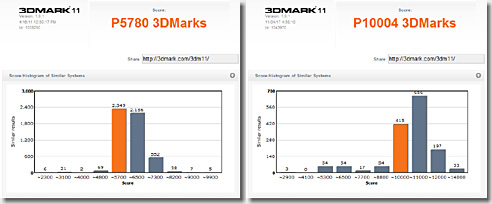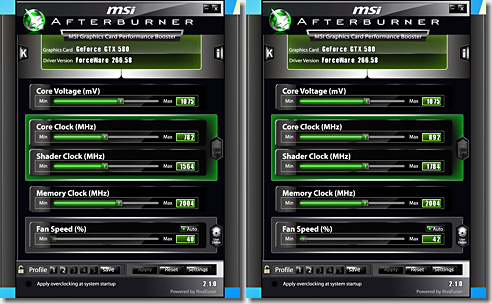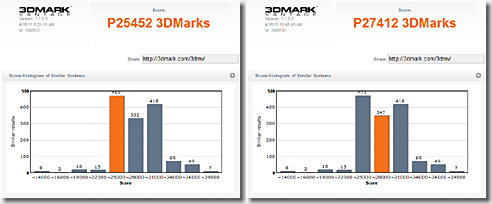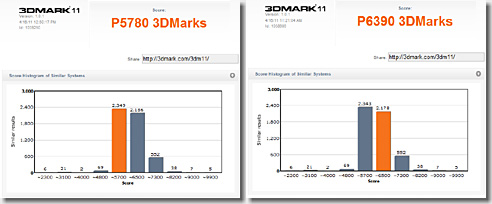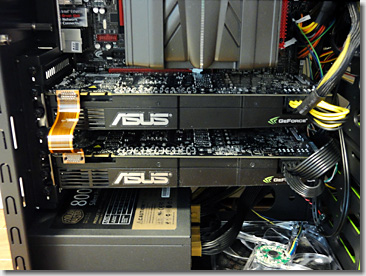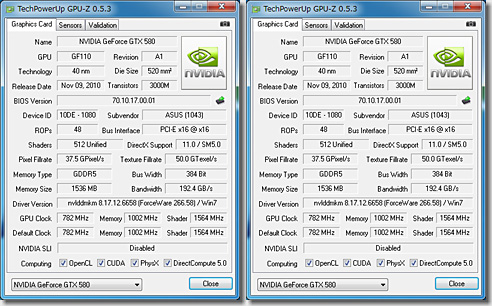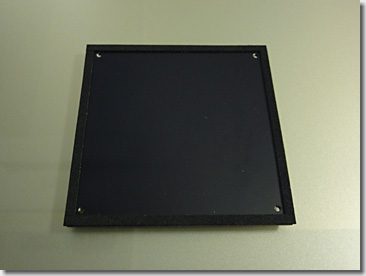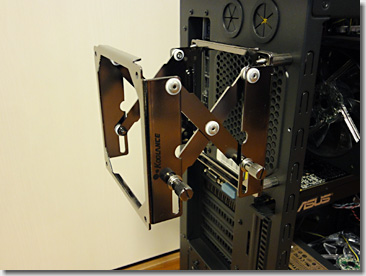ときどき、みょ~にプログラムが組みたくなることがある訳で、0xF9BE
工房blogのサイトマップは、MT5にテンプレートを組み込んで、エントリの作成時等に自動的に生成するようにしていますが、工房本体については、作っていませんでした。
そこで、ネット上の「サイトマップ作成サービス」を使って生成したのですが、さすがに無料なだけあって、更新日時等がかなりいい加減です。0xF9A5
仕方がないので、自分で作ることにしました。
ついでに、SEO対策として、「とある工夫」をすることにしました。
工房の各ページは、<frame>を使って構成していますが、<frame>を使ったページ構成は、Googleのサイトクローリングとは相性が悪いようです。
とはいえ、いまさらページ構成を大きく変えるのは骨が折れるので、解説ページなどを参考に、対策を打つことにしました。
(どのような対策を打ったかについては、別の機会に述べることにします)
まずは、その前段となる情報を生成します。
PHPスクリプトは、とても簡単です。(sitelink.php)
まず、サイトマップファイル(sitemap.xml)を読み出し、<loc>タグの間に記述されているURLを抽出し、配列($SitelinkArray)に格納します。
つぎに、URLからサーバ上のソースファイルのパス($SitesrcDataName)に変換し、そのファイルが更新された日時を得て、配列に格納します。
つづいて、サーバ上のソースファイルを読み出し、<title>タグの間に記述されているタイトルを抽出し、配列に格納します。
最後に、配列を、サイトマッププロトコルに基づいてサイトマップファイル(sitemap-new.xml)を出力し、終了します。
実行結果(画面)です。
このソースファイルをコピペして、SEO対策に使います。
実行結果(出力ファイル)です。
オプション情報は、<lastmod>タグだけを出力し、<changefreq>や<priority>は出力しないことにしました。
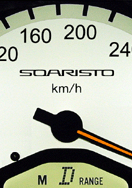
 Previous
Previous